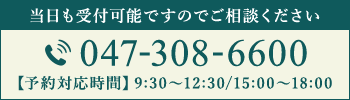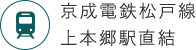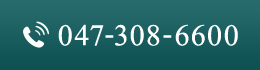足や足首の症状でお悩みの方
 当院では足や足首の症状や疾患ついて、整形外科専門医が丁寧に診療を行っております。
当院では足や足首の症状や疾患ついて、整形外科専門医が丁寧に診療を行っております。
下記のような足や足首の症状でお困りの方は、お気軽に当院にご相談ください。
- 足がだるい、違和感がある
- 足の痛みがだんだん強くなる
- 足が朝起きたときに痛む
- 足が歩いたときに痛む
- 足が座ったときに痛む
- 足が足を組んだときに痛む
- 朝起きたときに足の痛みやこわばりがあるが、時間が経つと痛みがなくなる
など
よくある足や足首の疾患
足関節捻挫
足関節捻挫は、足をひねったり、段差を踏み外すことで、痛みや腫れが生じます。外側の靱帯(前距腓靭帯)が損傷することが多く、スポーツでも日常生活でもよく見られるケガです。軽度の捻挫では、靱帯が伸びたり、わずかに損傷しますが、重度の場合は、靱帯が完全に断裂し足関節が不安定になります。その場合、痛みにより歩けなくなることもあります。
治療方法
初期段階での適切な対応が重要です。靱帯損傷は通常、3週間程度で痛みが改善しますが、放置すると関節が不安定になり、慢性的な痛みや変形性関節症を引き起こす恐れがあります。そのため、早期に治療を開始することが不可欠です。
軽度の捻挫の場合は、安静・圧迫・冷却・挙上を基本とした治療を行います。痛みや腫れがひどい場合は、シーネで足を固定し、しっかりと安静を保つことが必要です。2~3週間程度の安静が痛みの軽減に繋がります。また、治療後は再発予防のため、ゴムバンドを使用した筋力トレーニングを行い、足関節周りの筋力を強化します。
アキレス腱断裂
アキレス腱断裂は、特に30~50代のスポーツをしている方に多く見られる外傷です。腱の変性(老化)と過度な負担が原因で、ふくらはぎの筋肉が急激に伸縮する際に発生します。ダッシュやジャンプをしているときに、突然バットで殴られたような強い痛みを感じ、「パチン!」という破裂音が聞こえることもあります。断裂直後は足に体重をかけることができず、歩くことすら困難ですが、時間が経つと歩行できることもあります。しかし、つま先立ちができなくなり、日常生活に支障をきたすこともあります。
治療方法
まず保存療法を行います。ギプスや装具を使って腱を固定し、超音波エコーで状態を確認しながら6~8週間は安静を保ちます。スポーツに早く復帰したい場合や保存療法では改善しない場合、手術が推奨されることがあります。
外反母趾
外反母趾は、40代以降に多く見られる症状で、足の親指が人差し指に向かって「くの字」に曲がることによって、親指の付け根が内側に出っ張り、靴を履くとその部分が圧迫されて炎症が生じます。進行すると、靴を履くことすらできなくなり、素足でも痛みを感じることになります。この症状は、ヒール靴やつま先の狭い靴を長期間履き続けることによって、足の指が圧迫され、少しずつ変形していきます。更に進行すると、内反小趾を引き起こします。親指と人差し指の長さが均等でない方や、偏平足の方、関節リウマチの方はなりやすい傾向があります。
治療方法
ゆったりした靴を選び、外反母趾体操で足の指を広げる運動を行うことが重要です。さらに、親指と人差し指の間に装具を取り付けることで、変形を軽減することができます。痛みが強く、変形が進行している場合や胼胝(たこ)ができている場合には、手術を検討することになります。
扁平足
扁平足は、幼少期から土踏まずが平坦な場合、痛みを感じることは少ないですが、40代以降に発症することがあります。この場合、内側のくるぶしの下に痛みや腫れが現れ、加齢に伴う後脛骨筋腱の劣化が原因となります。特に女性に多く見られ、後脛骨筋の機能不全が起こると、足裏のアーチが下がり、バランスを取るのが難しくなることがあります。初期段階では、くるぶし周辺の痛みや腫れが主な症状ですが、進行すると歩行や立つことがつらくなる場合もあります。
治療方法
扁平足の予防や改善には、足指の筋力を高めることが重要です。裸足で過ごしたり、足指を積極的に使ったりすることで、足裏のアーチを支える力を強化できます。また、適正体重を維持することも重要です。アキレス腱が硬化しないようにストレッチを行うことも大切です。アーチが低下している場合は、足底板を使って足裏のサポートを行い、痛みを緩和することができます。痛みが続く場合は、手術も選択肢のひとつとなります。
モートン病
 モートン病は、40代以降の女性に多く見られる症状で、足の中指や薬指に痛み、しびれ、灼熱感が生じる病気です。足裏にできものを感じ、痛みがふくらはぎまで広がることもあります。長時間つま先立ちを続けることが原因で発症しやすく、足の中足骨間の神経が深横中足靱帯に圧迫されることで神経障害が起こります。その結果、痛みを伴う神経腫ができ、日常生活に支障をきたすことがあります。
モートン病は、40代以降の女性に多く見られる症状で、足の中指や薬指に痛み、しびれ、灼熱感が生じる病気です。足裏にできものを感じ、痛みがふくらはぎまで広がることもあります。長時間つま先立ちを続けることが原因で発症しやすく、足の中足骨間の神経が深横中足靱帯に圧迫されることで神経障害が起こります。その結果、痛みを伴う神経腫ができ、日常生活に支障をきたすことがあります。
治療方法
つま先立ちやハイヒールの着用を避け、局所の安静を保つことが大切です。また、薬物療法や足底板を使った装具療法、リハビリ療法などが症状に応じて行われます。痛みが強い場合は、局所麻酔やステロイド注射を行います。改善が見られない場合には、手術を検討することもあります。
痛風発作
 肥満や高血圧、過度な飲酒、食べ過ぎ、激しい運動などが原因で、血中の尿酸値が上昇すると、尿酸塩結晶が関節に沈着して、炎症を引き起こし、痛風発作が起こります。多くは、足の親指の付け根が急に赤く腫れ、激しい痛みが出ますが、アキレス腱や足の甲、手関節、膝関節にも現れることがあります。痛風発作をくり返す方は、違和感や軽い痛みなど、発作の前兆を感じることもあります。
肥満や高血圧、過度な飲酒、食べ過ぎ、激しい運動などが原因で、血中の尿酸値が上昇すると、尿酸塩結晶が関節に沈着して、炎症を引き起こし、痛風発作が起こります。多くは、足の親指の付け根が急に赤く腫れ、激しい痛みが出ますが、アキレス腱や足の甲、手関節、膝関節にも現れることがあります。痛風発作をくり返す方は、違和感や軽い痛みなど、発作の前兆を感じることもあります。
治療方法
痛風発作を繰り返さないためには、食生活の改善が重要です。野菜中心の食事に切り替えることで、尿酸値を抑えることができます。発作中の痛みには、消炎鎮痛剤を使って炎症を抑えます。また、激しい痛みがある場合には、ステロイドを使った関節内注射を行うこともあります。痛風発作が落ち着いた後は、尿酸値をコントロールするために、長期間の薬物療法が必要です。生活習慣を見直し、再発を防ぎましょう。
足底筋膜炎
足底筋膜炎は、特に40代以降の女性に多く見られる症状です。長時間立ちっぱなしでいたり、歩き続けていると、足底筋膜に集中して圧力がかかりやすく、足裏に痛みが生じます。
治療方法
足底筋膜やアキレス腱のストレッチが有効です。また、足底板をつけることで土踏まずにかかる圧を軽減します。痛みが改善されない場合には、足底筋膜の接地箇所に局所麻酔剤・ステロイド剤を注射する場合があります。しかし、クッションの役割を担っている脂肪変性や筋膜を断裂しかねないため、注意が必要です。