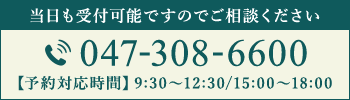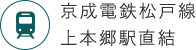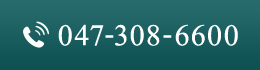腰部脊柱管狭窄症について
 腰の骨(腰椎)には神経が通っており、この神経は脊髄から出ています。腰椎の周りは、前には椎間板、後ろには靱帯という組織で囲まれています。何らかの原因で椎間板が変形し、後ろに飛び出してしまうことを「椎間板ヘルニア」といいます。また、靱帯が厚くなったり、骨が厚くなったり、腰の骨がずれて並んでしまうことで「腰椎すべり症」という状態になります。これらの問題が起こると、神経や脊髄が圧迫され、腰が痛くなったり、足にしびれや麻痺が出たりします。このような状態を「腰部脊柱管狭窄症」や「腰椎症」と呼びます。
腰の骨(腰椎)には神経が通っており、この神経は脊髄から出ています。腰椎の周りは、前には椎間板、後ろには靱帯という組織で囲まれています。何らかの原因で椎間板が変形し、後ろに飛び出してしまうことを「椎間板ヘルニア」といいます。また、靱帯が厚くなったり、骨が厚くなったり、腰の骨がずれて並んでしまうことで「腰椎すべり症」という状態になります。これらの問題が起こると、神経や脊髄が圧迫され、腰が痛くなったり、足にしびれや麻痺が出たりします。このような状態を「腰部脊柱管狭窄症」や「腰椎症」と呼びます。
腰部脊柱管狭窄症の原因
腰椎の脊柱管が狭くなる原因は、加齢に伴い、椎間板が変性したり、骨が変形したり、靱帯がゆるんだりすることです。また、もともと脊柱管が狭い人もいます。腰部脊柱管狭窄症は40歳以上の中高年に多く見られます。
しかし、足の血栓性静脈炎や動脈硬化症など血液の流れが悪くなることで、似たような症状が現れるため、正確な診断を受けるために、整形外科を受診しましょう。
腰部脊柱管狭窄症の症状
 腰椎の脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで、足に痛みやしびれ、力が入らないといった症状が出ます。歩き始めは問題なく歩けますが、少し歩いているうちに足が痛くなったり、しびれが出てきたりします。すると、歩くのが辛くなってきて、しばらく休むと痛みが和らぎ、また歩けるようになります。しばらく歩くとまた同じように痛みが出てきて、また休む…というのをくりかえします。この症状を間欠跛行といい、腰部脊柱管狭窄症特有の症状です。いつまでもこの症状が続くと、ロコモティブシンドロームという身体機能が低下した状態になることがあります。
腰椎の脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで、足に痛みやしびれ、力が入らないといった症状が出ます。歩き始めは問題なく歩けますが、少し歩いているうちに足が痛くなったり、しびれが出てきたりします。すると、歩くのが辛くなってきて、しばらく休むと痛みが和らぎ、また歩けるようになります。しばらく歩くとまた同じように痛みが出てきて、また休む…というのをくりかえします。この症状を間欠跛行といい、腰部脊柱管狭窄症特有の症状です。いつまでもこの症状が続くと、ロコモティブシンドロームという身体機能が低下した状態になることがあります。
ロコモティブシンドロームとは?
ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは、運動器症候群といい、立つ・歩くなどの移動にまつわる身体能力が低下した状態のことです。症状が進行すると、要介護となる可能性が高くなります。ロコモ度テストを実施したところ、ロコモ度1以上の方は、約4590万人いるといわれています。年齢を重ねても、自身の足で歩き続けるためにはロコモの予防を心がけることが大切です。
>>日本整形外科学会ロコモ度テストについてはこちらからご覧いただけます。
腰部脊柱管狭窄症の診断・検査
問診で、腰部脊柱管狭窄症特有の「間欠跛行」という症状があるかどうか確認します。
また、正確な診断をするためには、MRIや脊髄造影などの検査が必要です。しかし、足の血管が詰まって血液の流れが悪くなると、似たような症状が出ることもあるため、判別が必要です。必要に応じて、連携先の高次医療機関へ紹介させていただきます。
腰部脊柱管狭窄症の治療
腰部脊柱管狭窄症は、主に薬物療法・運動療法・ブロック注射を行って治療を行います。手術以外の治療法で症状の改善が見込める場合もあります。しかし、痛みが強くて歩けなくなってしまったり、排尿・排便障害が起こったりしている場合は、手術で神経を圧迫している箇所を切除する必要があります。
当院ではこれまでに3000件以上のブロック注射を行っておりますので、まずはご相談ください。
運動療法について
注意点
急な痛みや痺れがある場合は、症状を進行させないために、無理に動かさず安静にすることが大切です。だだし、安静にしてばかりいると、足の筋力や柔軟性はもちろん、体力が落ちてしまいます。そのため、症状が落ち着いてきたタイミングで、軽い運動を始めることをおすすめします。その際、腰を強く反らす、ひねるなどの動作は神経を圧迫し、症状が悪化する可能性が高くなりますので、避けるようにしましょう。
ウォーキング
歩くことは、足や腰の筋力を保つためにとても大切で、腰部脊柱管狭窄症があっても効果的です。ただし、痛みが強いと長時間歩くのが難しいため、無理をせず、翌日に痛みがひどくならない程度に毎日歩くことを心がけましょう。歩くときは、神経の圧迫を減らすために前かがみになったり、杖やシルバーカーを使ったりすることが役立ちます。しかし、ずっと前かがみで歩いていると、腰や背中に負担がかかり、将来的に痛みや筋肉のこわばりが出ることがあります。そのため、歩くときは無理せず休みながら、腰に負担をかけないように気をつけましょう。
自転車こぎ
自転車やエアロバイクは腰に負担をかけず、神経の圧迫を軽減できるので、運動に取り入れるのもおすすめです。