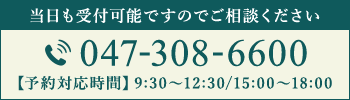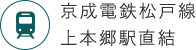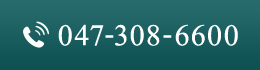骨粗しょう症について
 骨粗しょう症を発症すると、骨が脆弱になって、つまずいて手や肘をつく・くしゃみをするなどの日常の小さな衝撃でも骨折してしまいます。これは骨量が減少し、骨が弱くなることが原因となっています。骨粗しょう症は、日本人の死亡率上位に入る脳卒中・がん・心筋梗塞のような命の危険がある病気ではないものの、骨折が原因となって要介護になることがあります。日本の高齢化と共に増加傾向にある骨粗しょう症の患者様は、1000万人以上いるとされています。
骨粗しょう症を発症すると、骨が脆弱になって、つまずいて手や肘をつく・くしゃみをするなどの日常の小さな衝撃でも骨折してしまいます。これは骨量が減少し、骨が弱くなることが原因となっています。骨粗しょう症は、日本人の死亡率上位に入る脳卒中・がん・心筋梗塞のような命の危険がある病気ではないものの、骨折が原因となって要介護になることがあります。日本の高齢化と共に増加傾向にある骨粗しょう症の患者様は、1000万人以上いるとされています。
骨粗しょう症の原因
骨は新陳代謝を繰り返し、古く劣化した骨は新しい骨へと生まれ変わる性質を持っています。これを「骨のリモデリング(骨改変)」といいます。健康な骨は、絶えず作られたり(骨形成)、壊されたり(骨吸収)を繰り返すことでバランスを保つことができますが、骨粗しょう症を発症すると骨吸収のほうが進んで、骨の密度が低下します。骨粗しょう症の原因は加齢や女性ホルモンの減少によるもので、閉経後の女性に多くみられます。
閉経後の女性ホルモン(エストロゲン)低下
エストロゲンは女性ホルモンの一つです。このエストロゲンは、骨が新しく作られるときに骨が壊れるのをゆっくりにし、カルシウムが骨から出て行くのを抑制します。しかし、閉経後は女性ホルモンが減少するため、骨が壊れやすくなり、同世代の男性に比べて骨密度が低くなります。そのため、骨粗しょう症の患者様の約8割は女性です。
無理なダイエットや運動不足などの生活習慣
成長期は、丈夫な骨を作り、カルシウムを蓄える大切な時期です。しかし、過度なダイエットをすると骨密度が低くなり、骨粗しょう症になりやすくなります。また、運動不足の人も注意が必要です。運動が少ないと骨形成が活発に行われず、骨が老化しやすくなります。さらに、喫煙や飲酒も骨の健康に悪影響を与え、骨粗しょう症のリスクを高めます。年齢や閉経は避けられませんが、生活習慣を改善することは可能ですので、できることから積極的に取り組みましょう。
病気や薬が原因となる骨粗しょう症
骨粗しょう症の原因となる病気は、内分泌疾患である副甲状腺機能亢進症、糖尿病、関節リウマチや生活習慣病などがあり、骨の質そのもの劣化させて骨を脆くするものや、ホルモン不足によって骨代謝が悪くなり細胞に異常が生じて骨密度を低下させるものがあります。
さらに、ステロイド薬を長期的に内服した場合は、薬の副作用により骨粗しょう症を発症する可能性があります。
骨粗しょう症の症状
通常、骨粗しょう症を発症しても自覚症状はありません。
骨粗しょう症の症状チェック
1つでも当てはまるものがあれば、骨粗しょう症の可能性がありますので、
当院にて検査を受けることをおすすめします。
- 身長が縮んだ
- 背中・腰に痛みがある
- 背中・腰が以前より曲がったと感じる
日常生活の中で、このようなことがあれば骨粗しょう症の可能性があります。
- すぐに息切れする
- 少ない食事量で満腹になる
- 重い物を持つ時・立ち上がる時に腰痛が起こる
- 今まで着ていた衣服のサイズが合わなくなった
骨粗しょう症により骨折しやすい部位

- 背骨(脊椎椎体)
- 腕のつけ根(上腕骨)
- 手首(橈骨)
- 脚のつけ根(大腿骨近位部)
特に背骨は骨粗しょう症の影響を受けやすく、圧迫骨折が起こりやすくなります。圧迫骨折とは、身体の重みで背骨が押し潰れることをいいます。圧迫骨折は、腰や背中が曲がる原因になりますが、痛みを感じないことがあったり、ただの腰痛と考えて放置しがちです。1ヶ所でも骨折した場合、周辺の骨に負荷がかかることから、骨折が連鎖する可能性があります。そのため、早期発見・早期治療が大切になります。
大腿骨近位部骨折については、原因の85%が転倒によるものです。骨折してしまうと、歩行困難になり介護が必要になる可能性が高まるため、骨粗しょう症の治療と並行して転倒予防にも努めましょう。
骨粗しょう症の検査
問診
問診では、普段の食事内容・運動・病歴・生活習慣・閉経時期などの他に、現在気になっている症状を伺います。患者様からのお話が的確な診断を下す判断材料になっています。
X線(レントゲン)検査
レントゲンで背骨(胸椎・腰椎)の写真を撮ることで、骨粗しょう症とその他の病気を判別するとともに、骨折・骨の変形の有無などを確認します。
骨密度検査
 当院は、日本骨粗鬆学会のガイドライン推奨の検査方法である「DEXA(デキサ)法」を採用しています。日本整形外科学会の骨粗しょう症診断基準で測定が必須とされている腰椎と大腿骨の骨密度測定をアメリカ、ホロジック社の最新機器を用いることで、短時間で精確に検査することができます。そのため、骨粗しょう症の診断だけでなく、骨粗しょう症の治療の評価もできる検査です。
当院は、日本骨粗鬆学会のガイドライン推奨の検査方法である「DEXA(デキサ)法」を採用しています。日本整形外科学会の骨粗しょう症診断基準で測定が必須とされている腰椎と大腿骨の骨密度測定をアメリカ、ホロジック社の最新機器を用いることで、短時間で精確に検査することができます。そのため、骨粗しょう症の診断だけでなく、骨粗しょう症の治療の評価もできる検査です。
身長測定
骨粗しょう症の有無を診断する際、25歳の身長と現在の身長を比較してどの程度縮んでいるかを確認することが重要になります。
血液・尿検査
血液検査・尿検査によって骨代謝マーカーを測定することができます。骨代謝マーカーは、骨密度測定と合わせて使うことで、骨の健康状態や治療の効果を評価するために役立ちます。骨代謝マーカー値が高いと骨密度が低下するスピードが速いため、現段階で骨密度が高くても骨折する可能性は高くなります。また、この検査により、骨粗しょう症とその他の病気を判別することができます。
骨粗しょう症の予防と治療
 骨密度が加齢により低下する原因として、女性ホルモンの減少・腸管でのカルシウム吸収率の低下・ビタミンDの生成力の低下、若い頃と比較して食生活・運動量の変化が起こることも挙げられます。加齢は誰にでも起こる変化ですが、骨粗しょう症は予防が何より大事な病気であるため、若い頃から食生活・運動に気をつけて生活することで骨密度の減少を抑制することができます。
骨密度が加齢により低下する原因として、女性ホルモンの減少・腸管でのカルシウム吸収率の低下・ビタミンDの生成力の低下、若い頃と比較して食生活・運動量の変化が起こることも挙げられます。加齢は誰にでも起こる変化ですが、骨粗しょう症は予防が何より大事な病気であるため、若い頃から食生活・運動に気をつけて生活することで骨密度の減少を抑制することができます。
予防
- 転倒防止を心がける
- カルシウムを積極的に摂取する
- ビタミンD・ビタミンK・リン・マグネシウムを積極的に摂取する
- たんぱく質を適量摂取する
- 禁煙・節酒を心がける
- 運動・日光浴を心がける
- 閉経後は可能な限り、年1回骨密度検査を受ける
- 骨密度の減少を指摘された場合は、整形外科を受診する
治療
- 内服薬・注射を行う
骨吸収と骨形成のバランスを整える薬
・活性型ビタミンⅮ3製剤
・骨吸収を抑える薬
・ビスホスホネート
・SERM(サーム)
・抗RANKL(ランクル)モノクローナル抗体
骨形成をうながす薬
・副甲状腺ホルモン製剤
・抗スクレロスチンモノクローナル抗体
- 骨折の際は、適切な治療を行う