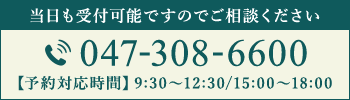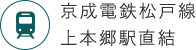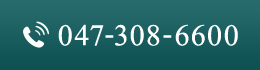足底筋膜炎について
 足底筋膜炎とは、足裏のかかとから足指の付け根をつなぐ線維である「足底腱膜」に炎症が起き、痛みを感じる病気です。「足底腱膜炎」とも呼ばれています。
足底筋膜炎とは、足裏のかかとから足指の付け根をつなぐ線維である「足底腱膜」に炎症が起き、痛みを感じる病気です。「足底腱膜炎」とも呼ばれています。
足底腱膜は、足のアーチ(土踏まず)を支えるとともに、足にかかる負担を和らげるクッションの役割を担っています。しかし、この腱膜が繰り返し引っ張られることでクッション機能が低下し、炎症が生じます。その結果、筋肉や骨に細かな損傷(微小断裂)や変性が起こり、痛みを引き起こします。
治療や予防には、負荷の原因を特定して改善することが大切です。
足底筋膜炎の原因
かかとからふくらはぎにかけての筋肉やアキレス腱が柔軟であれば、痛みが出ることはありません。足底筋膜炎を発症しやすい方の特徴として、アキレス腱やふくらはぎが硬い方はもちろんのこと、スポーツや激しい運動により足に負荷をかけている方、足を持ち上げる力が弱い方、足のアーチが下がっている方(偏平足)、加齢、肥満などがあります。
10~20代の方は激しいスポーツや運動により発症しやすいです。特に、ジョギングやランニングでは、アスファルトの硬い道路を長距離走るため、足の裏に強い衝撃を受けやすくなります。その他にも、長時間立ち続けることや疲労が溜まることでも同様に負担がかかります。なお、年齢を重ねることで特に激しい運動をしていなくても、足底筋膜の線維が弱くなるため、症状が出ることがあります。偏平足の方は、足裏のアーチが下がっているため、踵の骨に負担がかかり、足底筋膜炎になりやすい傾向があります。ハイヒールをよく履く方や、サイズの合わない靴を着用している方も、足裏に負担がかかるため、注意が必要です。
足底筋膜炎の症状
 長時間立ち続けることや歩き続けると、かかとの内側の前あたりに痛みが生じます。階段を上ったり、つま先立ちをしたりすると、痛みが増してきます。
長時間立ち続けることや歩き続けると、かかとの内側の前あたりに痛みが生じます。階段を上ったり、つま先立ちをしたりすると、痛みが増してきます。
ランニング開始時は痛みを強く感じますが、走っているうちにだんだん治まり、そのまま走り続けると痛みがまた強くなってきます。同様の症状は、40~60代の女性にも多く見られます。朝起きて最初の一歩目に痛みを感じますが、歩いていくうちに治まり、夕方になって活動量が増えると、また痛みが強くなってくることがあります。
足底筋膜炎の診断・検査
次のような症状があると、足底筋膜炎と診断されます。
- 押すと痛みが出る
足の裏の筋肉(足底腱膜)や、かかとの骨と筋肉がついている部分を押すと痛みが出ます。 - 痛みが出るタイミング
長時間立っていたり、歩いたり、走ったりしたときに痛みが出やすいです。
また、歩き始めた時に痛みが出ることもあります。
これらの痛みがあっても、別の病気が原因でないか確認します。
- 足根管症候群
- 後脛骨筋腱機能不全
- 反射性交感神経性萎縮症(RSD)
- 足底腱膜線維腫症
など
必要に応じて、レントゲンやMRI検査を行う場合もあります。
足底筋膜炎の治療
保存的治療
理学療法による治療
- 足の指から足首を反らせて、アキレス腱や足の裏の筋肉を伸ばします。足裏を伸ばすことを意識して、1回10回を目安に、1日に3回行うようにします。
- 足のアーチ(足の曲がり具合)に合った靴を選ぶことが大切です。また、かかとの部分に衝撃を吸収する素材が使われている中敷きを使うことも、痛みを和らげるために役立ちます。
薬物療法による治療
- 痛みを軽減するために、炎症を抑える効果のある薬を使用することがあります。
- 痛みが非常に強い場合は、かかとの部分にステロイド注射(注射で薬を直接痛む場所に届ける方法)を行うことがあります。かかとの脂肪組織の萎縮や腱膜断裂などのリスクがあるため、慎重に検討します。
手術療法による治療
保存的治療で改善しない場合や、重度の症状が続く場合には、手術が必要と判断されることがあります。この場合、かかとの骨にできた骨棘(骨の突起)を取ったり、足底筋膜の一部を取り除いたりする手術を行うことがあります。手術が必要な場合は、連携医療機関をご紹介いたします。
足底筋膜炎の予防

- 足裏の衝撃を減らす
歩いたり運動をしたりするときは、少しずつ強度を上げて、足や足首、ふくらはぎの筋肉に急激な負担をかけないように注意しましょう。 - こまめにストレッチをする
足底筋膜炎を予防するためには、足や足首、ふくらはぎの筋肉を柔軟に保つことが重要です。そのために、ストレッチを行うようにしましょう。ストレッチは、筋肉の疲れを取り、足底筋膜の疲労回復にも役立ちます。朝起きたとき、長時間歩いたり走ったりした後、お風呂上がりなど、これらのタイミングでストレッチを行うと、効果的です。 - 足に合った靴を選ぶ
歩いたり運動をするときに足裏にかかる衝撃を和らげるために、足裏に衝撃吸収材がしっかり入っている靴を選びましょう。また、自分専用のインソール(靴の中敷き)を使うことで、さらに衝撃を減らすことができます。