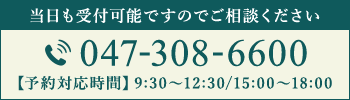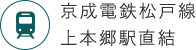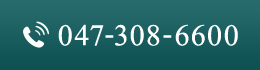ぎっくり腰
(急性腰痛)について
 ぎっくり腰とは、病名・診断名ではなく、一般的に呼ばれる通称です。正式には「急性腰痛」と言います。物を持ち上げたときや腰を捻じったときに起こることが多いですが、起床直後にも起こることがあります。強い痛みがある場合には、ぎっくり腰ではなく、重大な病気が隠れていることもあるため、手遅れになることがないよう、はやめに当院までにご相談ください。
ぎっくり腰とは、病名・診断名ではなく、一般的に呼ばれる通称です。正式には「急性腰痛」と言います。物を持ち上げたときや腰を捻じったときに起こることが多いですが、起床直後にも起こることがあります。強い痛みがある場合には、ぎっくり腰ではなく、重大な病気が隠れていることもあるため、手遅れになることがないよう、はやめに当院までにご相談ください。
ぎっくり腰
(急性腰痛)の原因
ぎっくり腰の原因は不明
ぎっくり腰の原因は、まだはっきりとわかっていません。脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニア、腰椎圧迫骨折などの病名がつかない強い腰の痛みは全てぎっくり腰といえます。
しかし、ぎっくり腰が起きたときに共通していることは、重い物を持ち上げたときやくしゃみや咳をしたとき、落ちた物を拾おうとしたとき、軽くお辞儀をしたとき、立ち上がったときなどが、日常生活でのふとした中腰の動作がきっかけとなっています。中腰の姿勢は、椎間板に負荷がかかりやすく、ヘルニアなどの腰に持病がある方には注意が必要な姿勢です。
また、起床直後に起こるのは、寝ているときに椎間板が伸びるため、椎間関節は油ぎれの状態であるなか、急に起き上がると、力学的にスムーズ動きができないため、椎間板に負荷がかかるとされています。
ぎっくり腰ではなく、別の病気が隠れていることも
痛みがあっても歩けるのでしばらく様子をみたり、マッサージを受けたり、ご自身で対処してしまうことで、腰の痛みが悪化してしまうこともあります。
腰の痛みが2週間以上改善しない場合や、痛みをくりかえす場合は、ぎっくり腰ではなく、他の病気が隠れていることがあるため、整形外科を受診し、診断を受けることをおすすめします。
ぎっくり腰と似た症状が出る病気・ケガ
- くりかえし、ぎっくり腰を患っている場合は、「椎間板ヘルニア」
- 骨粗しょう症がある場合は、「脊椎の圧迫骨折」
- 腰痛だけでなく、足の痺れがある場合は、「脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニア」
などが考えられます。
ぎっくり腰
(急性腰痛)の症状
- 少しの動作で腰に激痛が走る
- しゃがむことができない
- 急に腰に強い痛みが起こる
- くしゃみ・咳で腰に痛みが出る
ぎっくり腰
(急性腰痛)の診断・検査
 ぎっくり腰の診断には、腰痛が起こっている場所・症状・どのような動作で痛むかなどを診察で伺います。数日経過しても痛みがなくならない場合、レントゲンで骨の形・骨の間隔・骨折をしているかなどを確認します。必要に応じて、MRIにて、レントゲンでは確認できない椎間板や神経を確認し、圧迫骨折や腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰部以外の病気の有無を調べます。その際は、連携医療機関を紹介させていただきます。
ぎっくり腰の診断には、腰痛が起こっている場所・症状・どのような動作で痛むかなどを診察で伺います。数日経過しても痛みがなくならない場合、レントゲンで骨の形・骨の間隔・骨折をしているかなどを確認します。必要に応じて、MRIにて、レントゲンでは確認できない椎間板や神経を確認し、圧迫骨折や腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰部以外の病気の有無を調べます。その際は、連携医療機関を紹介させていただきます。
ぎっくり腰
(急性腰痛)の治療・予防
治療
保存療法が基本的な治療法です。症状が強い場合はコルセットを着用し、できるだけ腰を安静にします。炎症を抑えるため、内服薬・湿布などを用いて治療を行います。急性期を過ぎて痛みが少し治まって動くことができるようになってきたら、今までの生活に戻していくことが早期回復への近道です。コルセットの使用は必要最小限にして生活することが大切です。ぎっくり腰が完治したら、腹筋・背筋の筋肉だけでなく、体幹全体の筋肉を鍛えることでコルセットの役割を果たし、腰を守ります。
予防
 ぎっくり腰の原因がわかっていないため、明確な予防策はありませんが、ぎっくり腰を起こすきっかけを知り、日々の生活の中で意識することが大切です。
ぎっくり腰の原因がわかっていないため、明確な予防策はありませんが、ぎっくり腰を起こすきっかけを知り、日々の生活の中で意識することが大切です。
運動不足による筋肉の衰えや、デスクワークなど長時間同じ姿勢でいることは、あらゆる筋肉を硬直させ、腰椎の柔軟性を維持できなくなります。
日常生活の中で正しい姿勢を意識したり、ウォーキングやストレッチを積極的に行ったりすることで、肩・背中・腰などの筋肉や関節に柔軟性を持たせることができます。
床の荷物を持ち上げる時
床の荷物を持ち上げる際は、股関節・膝を曲げ、腰を落として荷物を持ち上げます。下腹を前に出して身体のS字カーブが維持できる姿勢を保つことが大切です。立った状態で腰を曲げたり、腕の力だけに頼ることなく、足の力も活用してゆっくりと持ち上げるようにしましょう。
起床時
ぎっくり腰などの腰回りのトラブルは、身体の硬さも原因となっています。起床時は急に上体を起こすのではなく、一度横向きになって手で支えながら起きたり、布団の中で軽くストレッチをして身体をほぐしたりすると、ぎっくり腰を避けることができます。
くしゃみ・咳をする時
急に前かがみの姿勢になることで、ぎっくり腰を起こしやすいため、くしゃみや咳が出そうになったら、壁などに手をつくと、腰の負担を軽減できます。また、できるだけ上体を起こしながら、腰を少し反らしてS字にカーブするような姿勢をとるように意識することで、くしゃみや咳の衝撃から腰を守ることができます。